【要約】『Think Bigger』で“発想を設計する力”を鍛える:6ステップで学ぶ創造の技術
■ なぜ今、「創造の力」が必要なのか
AIが台頭し、過去の成功モデルが通用しづらくなっている今、求められるのは“新たな問いを立てる力”です。問題をどう捉え、どう組み替え、どうアイデアに昇華するか──それこそが、人間にしかできない創造的思考です。
本書『Think Bigger』の著者であるシーナ・アイエンガーは、コロンビア大学ビジネススクール教授として「選択と意思決定の科学」を研究してきました。その彼女が提示するのは、発想を「6ステップ」で構造的に育てていく思考法。
この記事では、その要点を要約しながら、あなた自身の思考の「設計力」を高めるヒントを紹介します。

■ 『Think Bigger』の全体要約:創造は“プロセス”である
創造とは、天才の閃きでも右脳の魔法でもありません。著者が説くのは、既知の情報や素材を「組み合わせ直す」ことで新しい価値を生み出す力。
この考え方は、「知っているつもり症候群(Knowledge Illusion)」への警鐘でもあります。重要なのは、問題をどう見るか。すべてはそこから始まります。
■ 6ステップ・メソッドの実践解説と要約
ステップ1:「問題を選ぶ」
どんな問題に取り組むかが、発想の出発点になります。ここでは、私たちが無意識に避けてしまう「本質的な問い」に立ち戻り、「挑戦する価値のある問題」を見極めます。
要約:問いの質が、発想の深さを決める。
ステップ2:「問題を分解する」
ひとつの課題を構造的に分解し、サブ問題として捉えることで、複雑さの本質に迫ることができます。分解は、見落としていた視点を発掘する作業でもあります。
要約:問題は“洗い出し”によって磨かれる。
ステップ3:「誰の望みかを比較する」
自分、対象、そして第三者──それぞれが持つ欲求(Wants)を比較・分析し、「Big Picture Score(発想の全体評価基準)」を設計します。
要約:他者の視点を織り込んでこそ、発想は開かれる。
ステップ4:「内箱・外箱を検索する」
解決策は、思わぬ場所から生まれることもあります。自分の専門領域(内箱)だけでなく、異業種・他分野(外箱)にも目を向けることで、アイデアの素材が飛躍的に広がります。
要約:発想は、視野の広さに比例する。
ステップ5:「チョイスマップを作る」
ここでは、サブアイデアを組み合わせて具体案を設計する段階。複数案を可視化し、選択肢を整理する「組み合わせ地図(Choice Map)」をつくることで、思考は一気に実用化へと向かいます。
要約:発想を“見える化”することで、選べるようになる。
ステップ6:「サードアイ(第三の眼)テスト」
最後に、他者の目を借りて自分の案を再評価する工程です。フィードバックを受けながら、自らの言葉で語り直すことで、アイデアはさらに洗練されます。
要約:自分の発想を、他者に語れるか? それが真の完成度を示す。
■ この本が教えてくれる“創造の真実”
『Think Bigger』が特別なのは、「誰でも発想できる」ことを証明してくれる点にあります。視覚障害を持つ著者自身が、目ではなく“視点”で考える力を養い、「第三の眼」という発想法にたどり着いたことが、本書の説得力を高めています。
また、脳科学や意思決定理論といった裏付けのある内容が、単なる自己啓発を超えた「実学」としての信頼を支えています。
■ 読者・専門家の評価と議論
本書は、《Financial Timesの2023年ビジネス書トップ10》にも選ばれ、世界中のビジネスパーソンや教育者に高く評価されています。
ただ一方で、「すべてを6ステップで解ける」と思わせる過剰な一般化には注意が必要、という慎重なレビューも見られます。
詳しい解説や書評は、以下の記事も参考になります:
👉 理念と経営WEB|『Think Bigger』解説
■ まとめと行動への誘い
創造は、選ばれた人だけの特権ではありません。『Think Bigger』は、問いの設計から発想の組み合わせ、他者視点の導入まで、「考える力を育てるための手順書」として、誰にでも開かれた実践書です。
あなたもまず、次のように始めてみませんか?
- 「自分が本当に解決したい問題」を書き出してみる
- それを6ステップに照らして、視点を拡げてみる
- 今日から一歩、「ビッグピクチャースコア」を描いてみる
このような思考法に興味のある方は、知的好奇心を刺激する本との出会いがきっとあるはずです。Dear Bookのおすすめ書籍一覧も、ぜひ参考にしてみてください:
👉 Dear Bookおすすめ本リスト(内部リンク)
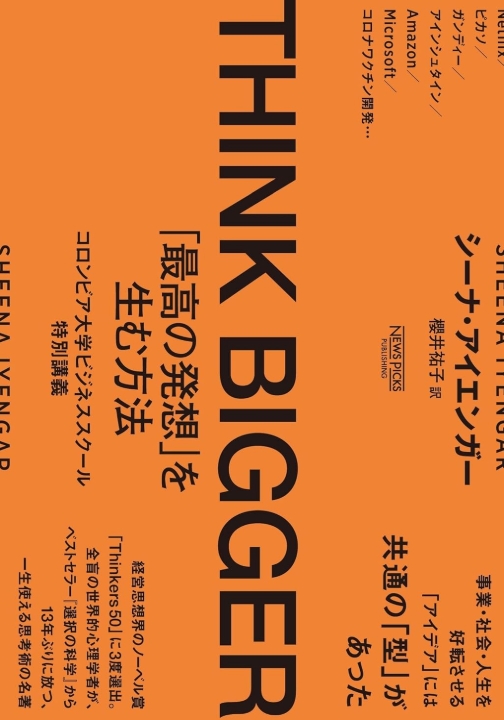
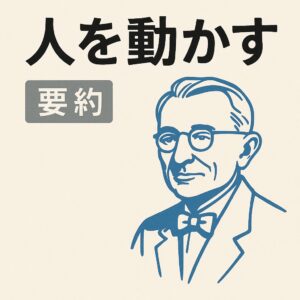
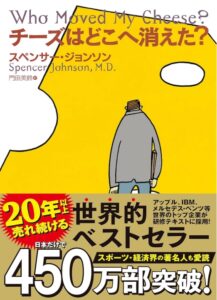
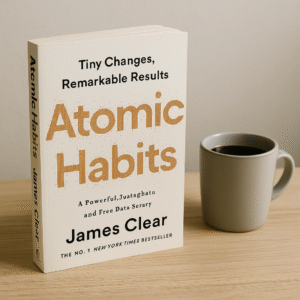
コメント